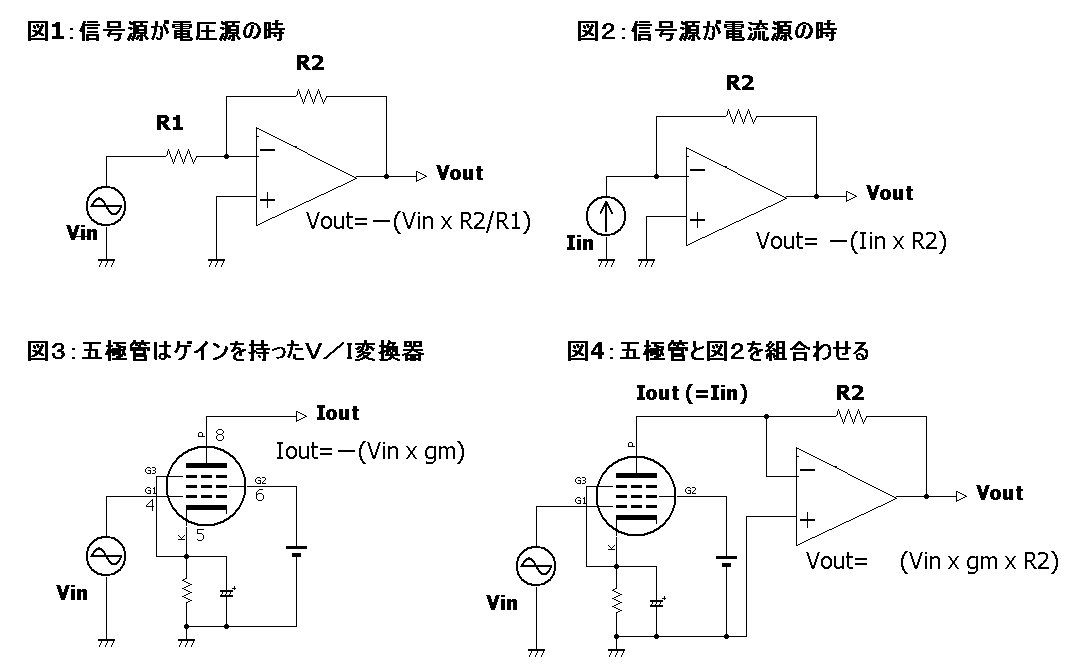
|
D級100Wアンプ基本設計 |
[真空管とD級アンプの接続方法]
このアンプの回路の要点は、真空管とD級アンプをどのように結びつけるかです。単純にラインアンプをD級アンプの前に配置して一体型のケースに収めても、真空管サウンドを楽しむことは可能かと思いますが、もう一ひねりしてみたかったわけです。
今回採用するIR社のIRS2092のデータシートを眺めていたら、このICは、単純にパーワーが大きなオペアンプの構成を取っていることがわかりました。ICの中ではPWM変調を行っているので、高域のF特に関しては通常のオペアンプと同じになりませんが、スイッチング周波数である約400KHz以下の周波数領域ではオペアンプとして取り扱ってかまいません。そうであるならば、『トランスインピーダンス回路』を形成して、五極管の高いインピーダンスで電流ドライブしたら面白かろうと思った次第です。
オペアンプの基本動作に関しては、ネットでいくらでも調べることができますが、以下の図によって簡単におさらいします。
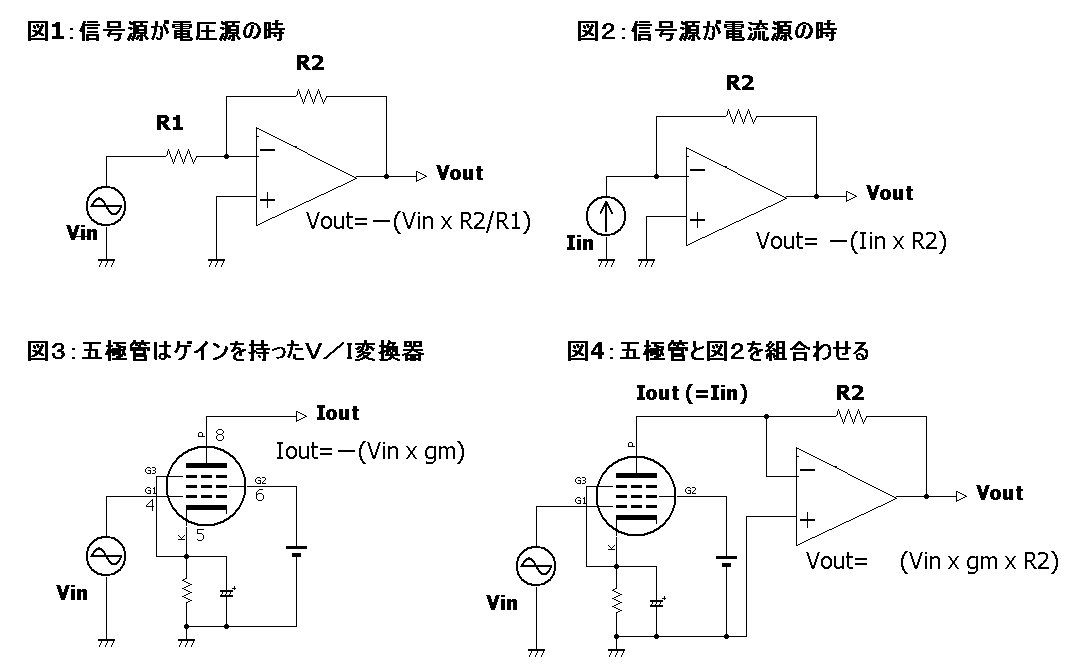
図1が反転増幅の基本形で、そのゲインはR1とR2の比で表わすことができます。つまり、R1=1KΩ、R2=15KΩならばこの回路のゲインはマイナス15倍となります。「マイナス」の意味は位相が反転していることを表わします。
図2は、図1の信号源が電圧源であったのを電流源としたものです。電流源は内部抵抗が無限大ですから、直列にR1の有限値の抵抗を加算しても意味が無く、R1は消してあります。信号源から流れ出した信号電流(Iin)アンペアは、全量がR2に流れ込みます。なぜならば、オペアンプ入力は無限大のインピーダンスのため流れ込むことができず、全電流がR2を流れざるを得ないからです。従ってR2の両端にはオームの法則により、Iin x R2の電圧が発生していることになります。R2の左端の電位は「イマジナリショート」により、非反転入力とほぼ同じで、この回路の場合GND電位になります。従って、R2右端の電位はマイナス(Iin x R2)ボルトになります。
図3は五極管の増幅回路を簡略化して書いたものです。五極管は三極管と違って内部抵抗がきわめて大きく(今回採用の6SJ7では約500KΩ)、電流源出力として取り扱っても大きな誤差はありません。五極管の第一グリッドにVinの信号を加えるとプレート側には電流源出力として、マイナス(Vin x gm)アンペアの出力が得られます。「gm」は真空管の「相互コンダクタンス」です。
図4は今回採用した回路を模式化したもので、図2と図3をシリーズに接続したものです。五極管で電流源変換されたIoutはそのままオペアンプのIinとなり、R2に流れます。図4の出力は、図2の式に図3の式のIoutをIinと書き換えて代入すれば、Vout=(Vin x gm x R2)が得られます(真空管で位相が反転し、オペアンプでも反転しますので、アンプ全体では反転しない動作となります)。
つまり、このアンプは、入力信号であるVinを単純に(gm x R2)倍して出力するだけです。R2は固定抵抗ですから、良質なものを使えば非直線性は無いとして扱ってかまいませんが、gmは一定ではなく、入力信号レベルに対応して変化します。この非直線性が、いわゆる「真空管サウンド」を形成しているのではないかということが本機の狙いの一つです。今回は五極管として、6SJ7を用いましたが、他の五極管を使えば直線性が異なります。また、三極管を使えば、電圧ドライブと電流ドライブの中間的な動作になりますから異なった音を楽しむことができるでしょう。
[電流帰還について]
以下は、今回のアンプの原理を説明するための基本ブロック図です。
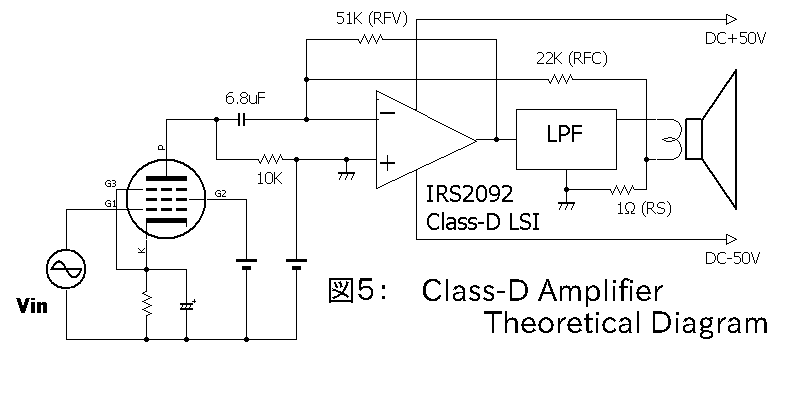
前項で、D級アンプを電流源ドライブする本アンプの基本構想を説明しました。ここでは、もう一つの特長である「電流帰還」について説明します。
真空管との接続は直結として構成することも可能ですが、ドリフトや電源の複雑化をきらい、今回はAC結合を用いました。上の図の6.8μFがカップリングコンデンサーです。その下の10KΩはプレートのバイアス電流を流すための抵抗です。図5において、51KΩ(RFV)が前項で説明したR2に該当する電圧帰還抵抗です。
本機では、上記、電圧帰還に加えて電流帰還もかけてみました。理由として、私の持っているスピーカーはダンピングファクターを上げすぎずにDF=2前後にしておいたほうが音が良いためです。私の自作真空管アンプは、DF=2〜4位に設計するのが常です。半導体アンプでは、このような低いDFを作り出すのが難しいですが、電流帰還を使えば達成できます。
1Ω(RS)はスピーカーと直列に入っているのでボイスコイルの電流と全く同じ電流が流れます。したがってその両端にはボイスコイル電流に比例した電圧が発生しています。この電圧を22KΩ(RFC)を介して帰還することにより、電流帰還が達成できます。ここで注意しないといけないのは、電圧帰還がLPFの手前から帰還されているのに対して、電流帰還はLPF後となります。電流帰還も負帰還ですから、帰還量を増やすとせっかくのLPFの減衰特性を平坦化させ、フィルタの切れが悪くなってしまうことです。本機では電流帰還を欲張らないように少なめにしておきました。LPFの減衰特性も変化しましたのでシミュレーションにより最適値をもとめました。その結果、コイルのインダクタンスは60μHとなり、今までに発表例がない大きな値になりました。コイルの巻数が大きくなり直流抵抗が増加しますので、コイルの選択には悩みましたが、ジャンク屋で以下のような良いものを見つけ、ブログで報告してあります。
http://ja1cty.at.webry.info/200906/article_3.html
2009年8月24日現在のアンプ回路図は以下です。入力信号を単純に(gm x R2)倍するだけなのに結構複雑な構成になります。
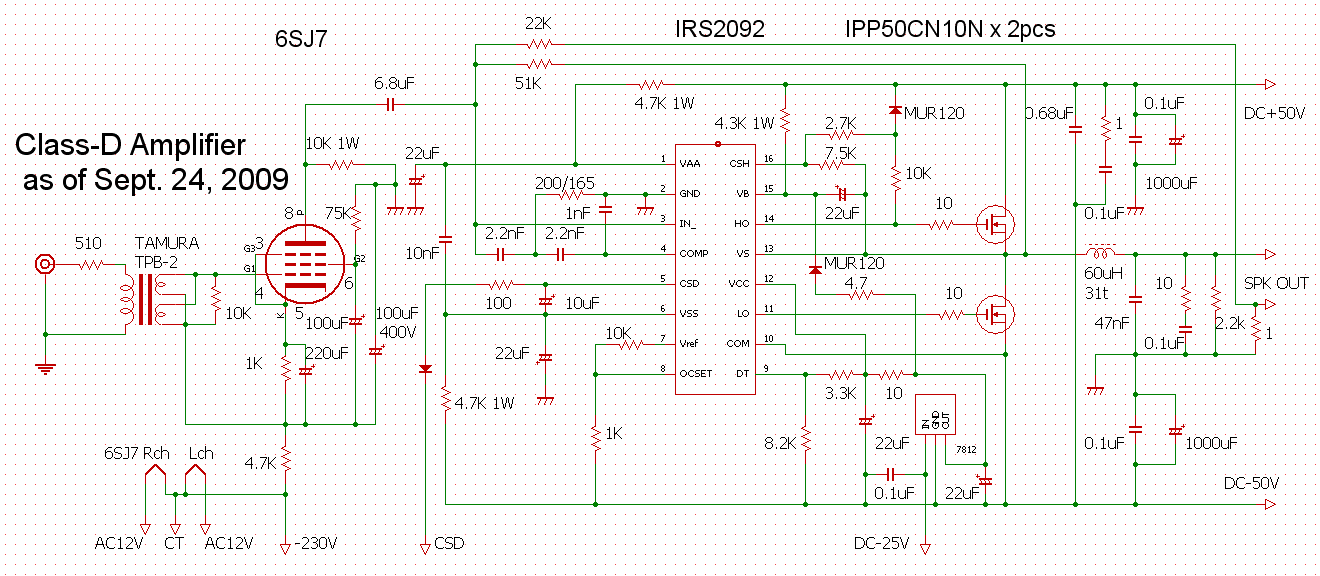
(2009.9.28)