お父さん族のためのパソコン教室顛末記
葛山 洋一 (旭丘14期)
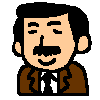
|
お父さん族のためのパソコン教室顛末記
葛山 洋一 (旭丘14期)
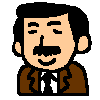
|
|
毎朝の通勤バスの中で新聞を拡げるのだが、それが段々と困難になり、ついには前の座席の背もたれが邪魔になったので、ある日、とうとう決心をして、町の眼鏡屋へ出かけた。
店の者に「老眼鏡の売場は・・・・・」と尋ねかけたが、なかなかその一言が出てこない。そうと察した店員は、つっと傍に寄り「お客様、シニアグラスをお探しでしょうか?」と言う。なるほど、旨い応対だ。
お陰で、もう前のシートが障害になることもなく、小さな文字までも楽々と読めるようになったのは嬉しかった。しかし、初めての眼鏡は何ともうっとうしく、そればかりか急に老け込んでしまったように思え、そぞろ侘びしい気がしたものだ。 世の中は、ディスコ・カラオケ・Jリーグと、今や若者文化の花盛りである。特に週末のアフターファイブの盛り場などには、元気溌剌のOLや新人たちが溢れ返って眩しいほどだ。我々お父さん族は、その横をそっとすり抜けて家路に就く。ムリもない。何と言ったって戦中戦後生まれだ。目はかすみ、歯は抜ける、記銘力・起想力の減退も疾に自覚しているから、手帳のお世話になって随分と久しい。今更若造の真似なぞ出来るか。諺にも「君子危うきに近寄らず」と言うではないか。
ところが未曾有のバブルが弾け、リストラの嵐が吹きまくったその後に、世は挙ってビジネスプロセス・リエンジニアリングとばかりに、コンピューターテクノロジーによる改革に傾斜し始めた。すなわち、世界標準パソコンとインターネットによる新しい企業情報化の時代の幕開けという次第だ。わが社においても遂にイントラネット構想が打ち出され、一人一台のパソコンを配備し、業務改善に向かって邁進せよ、との檄が飛ばされた。 さあ、情報システム部門の責任者としては、もはや自分の眼鏡のことなどを嘆いている暇はなくなった。これまでの古いシステムをどうするか、一〇〇〇人もいる支店社員の教育は?、お金のやりくりは?、技術要員の教育訓練は?、など悩みはつきない。中でも中高年管理職、すなわちテレビのリモコンがせいぜいの「お父さん族」を、どのようにしてパソコンの前に座らせるかが問題だ。これは難しい。思案の日々が続いた。 ある日のこと、我が敬愛するご年輩の上司から、「若い人たちは元々好奇心が旺盛だから放っておいても大丈夫だろう。しかし中高年に対しては、先ずはパソコンに対する心理的なバリヤを下げることが鍵だよ」と言われた。なるほど、あの眼鏡屋の遣り口か。
秋も深まるある日曜の午後、ベランダでコーヒーを啜り、タバコをくゆらせながら「お父さんのためのパソコン教室」の構想を練った。
次は、具体的な中身や運営方法である。究極の目的はもちろん電子メールを使って戴く処にある訳だが、いきなりでは必ずやメゲてしまうであろうから、履修する科目とその順番はインターネット/ワープロ/電子メールとする。講習は各単元とも二時間とする。仮に一日かけて詰め込んだとしても、とても覚え切れるシロモノではないし、第一、幹部たるものは一日中座っていられるほど暇ではない。事情が許せば個人教授としたいところだが、ここは目をつぶって六人を一組の集合教育方式とし、インストラクタとアシスタントの二名を付ける。場所は専用のOAルームだ。この方が職場の部下の冷たい視線に晒されることも無いので、かえって都合が良いだろう。
基本構想が出来てしまえば、後はテキストの選定だけだから簡単なことだと考え、早速、新聞の広告欄でチェックしておいた「初めての○○」だとか「サルでも出来る××」というビギナー向けの本を探しに出かけた。しかし、いざそれらの本を手に取ってみると、やはり懸念した通りコンピュータ用語の氾濫で、とても中高年ビギナー向きとはいえない。そこで、今度は部下に言いつけて作らせてみたが、熟知していることを細々と書き連ねてゆかねばならないことは結構苦痛な作業であることに加え、まだほんの若者だから、中高年の特異性がよく理解できない。再々の書き直し命令に、遂にはムクレ始めた。仕方ない、ここは自分で作るしかあるまい。そう決心して、スイッチの入れ方と消し方から始まり、マウス操作など、基礎の基礎から教程教案を練り、それに基づいてテキストを作成していった。この作業は、既に立派な中高年である自分自身をモルモットにして検証できるという点ではメリットがあったが、なにしろ年寄りの冷や水だから、思いの外に時間を喰ってしまった。
さて、こうして準備も整い、いよいよオープニングである。
それからである。職場では若い部下を捕まえて「どうだこれがインターネットだ」と少々エッチなページを得意げに披露する専門部長さん。また、覚えたばかりの電子メールで「卒業のお礼に一献さしあげたいが、今夜のご都合はいかが?」とメッセージをくれる幹部さん。自宅にもパソコンを入れたいからディーラやインターネットのプロバイダを紹介して欲しいという経営幹部さん。中には「ウィンドウズ出来ぬ人から窓際へ」など、少し前ならきっと自分がムッとしたであろうような川柳を嬉しげに教えてくれる人まで現れた。廊下やエレベータではインターネットやウィンドウズに関する話題や質問が飛び交うなど、波紋は急速に拡がり、社内ではちょっとしたパソコンフィーバが始まった。目論見通りである。
時の経過と共に、噂を聞きつけた一般の中高年も続々と応募してくれるようになった。中には来年ご卒業となる方の応募もあり、人事部門の渋い顔が目に浮かんだが、職場の活性化の効果も期待できることでもあるし、ここは永年勤続表彰の一種と割り切って、可能な限り門戸を開いた。
こんなとき、ある先輩に「それにしても君も好きだね〜エ」と揶揄された。確かに好きは好きではある。また、元々が自己顕示性の性格のためかもしれない。しかし「中高年ためのパソコン教室」に力を注いできたのは決してそればかりではない。
さて、日曜日の午後である。初夏の日差しを浴びながらベランダに座り、例によってコーヒーを啜りタバコをふかしながら考えていた。 この「お父さんのためのパソコン教室」、商売にしたら案外あたるかもしれない。 何と言ったって 中高年層は団塊の世代でもあるのだから、お客には事欠かないだろう。それに自分のサラリーマンライフも、もう第四コーナにさしかかっている。ぼちぼち定年後の算段も考えておかなくては・・・・・。 例えば、郊外に小さなオフィスを借りて・・・、賃貸しのWWWサーバも置き、こちらの方は二四時間のフル操業だから、経営者の自分が寝ている間も勤勉に稼いでくれる。孫娘のような可愛らしいアシスタントを何人か雇って、白髪頭のお爺さんが、昼はホームページを作り・・・・・、これはコンピュータ知識よりもデザインが勝負だから若い奴には負けないぞ。そして夜は中高年教室だ。旨く行けばそれなりに食べてゆけるし、創造的な仕事だから結構楽しいかもしれない。或いは郊外ではなくて、灯台の見える海辺に瀟洒なコッテージ風の事務所なぞを開いて・・・・・、うん、そういえば、あのヨシコちゃんも老後は海辺の別荘で本を書いて暮らしたいわ、と言っていた・・・、などと他愛のない夢をウトウト見ていたら、突然耳もとで 「あなたっ! タバコの灰がっ!」という割れ鐘のような大きな声が響きわたり、いっぺんに目が醒めてしまった。
1996年 初夏
|